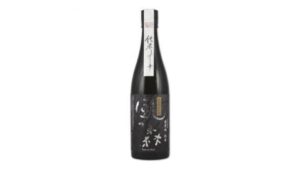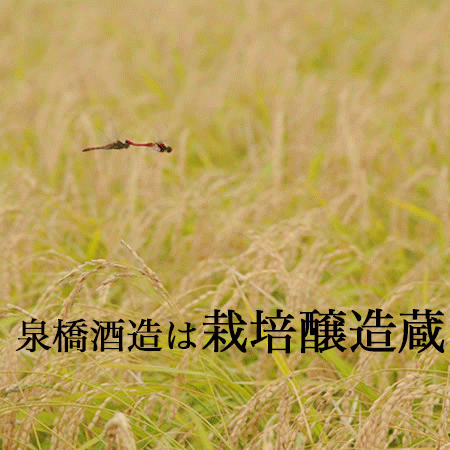
泉橋酒造
泉橋酒造は「酒造りは米作りから」の信念のもと、酒米作りから精米・醸造まで一貫して行う栽培醸造蔵です。
- 代表者: 橋場 友一
- 本社所在地: 〒243-0435 神奈川県海老名市下今泉5−5−1
- 電話番号: 046-231-1338
- 創業: 江戸・安政4年創業、西暦1857年
- 公式HP
brewery profile 蔵元について・受賞歴など
泉橋の由来~地元の農業と共に~
江戸・安政4年(1857年)創業


蔵の北側の圃場から

酒米研究会の伊波氏と蔵元
昔の写真から泉橋酒造の姿を考える~泉橋の由来~
泉橋酒造の社名にもなっている「いづみ橋(泉橋)」の由来の話ですが、古来からの農業環境そのものに端を発しています。 以下は、昭和2年(1927年)の旧日本陸軍が撮った航空写真を使って説明します。 中央に泉橋酒造とその北側の海老名耕地に泉川(いづみがわ)が流れています。この泉川は田んぼの用水路の役目を果たしていたことがよくわかります。 また、うちの屋号が「橋場(はしば)」だったことから、泉川+橋場=泉橋となったのことです。水田の穀倉地帯からの命名だったことがわります。 次にわかりやす泉川の位置と弊社の位置を入れてみました。
次にわかりやす泉川の位置と弊社の位置を入れてみました。
 しかしながら、泉川は、昭和5年から10年の歳月を掛けて行われた土地改良事業によってまっすぐな用水路に姿を変えてしまい、
現在では泉川は存在していませんが、泉橋酒造の名前に生きています。
しかしながら、泉川は、昭和5年から10年の歳月を掛けて行われた土地改良事業によってまっすぐな用水路に姿を変えてしまい、
現在では泉川は存在していませんが、泉橋酒造の名前に生きています。
 上の写真は、昭和47年に米軍が撮影した写真です。泉川はなくなりましたが、代わりに田の区画が大きく、きれいになっています。この後の農作業の機械化などに対応し農業環境がよくなったのでしょう。そして、今の泉橋酒造(株)があります。地域の諸先輩たちに感謝ですね。
現在の航空写真は次をご覧ください。写真はすべて国土地理院から購入したものです。
上の写真は、昭和47年に米軍が撮影した写真です。泉川はなくなりましたが、代わりに田の区画が大きく、きれいになっています。この後の農作業の機械化などに対応し農業環境がよくなったのでしょう。そして、今の泉橋酒造(株)があります。地域の諸先輩たちに感謝ですね。
現在の航空写真は次をご覧ください。写真はすべて国土地理院から購入したものです。

明治期の橋場酒造店(現在の泉橋酒造)

並んだ木桶
泉橋の酒造り
酒造りは米作りから・・・
 泉橋酒造は、「酒造りは米作りから」の信念のもと、全国でも珍しい「栽培醸造蔵」として海老名市をはじめ近隣地区で酒米栽培から精米・醸造まで一貫して行っています。 太陽と大地の恵みをいっぱいに受けて育んだ信頼できる米を丁寧に仕込む、それが私達の酒造りです。いづみ橋を囲みながら仲間同士で話が弾み、杯を重ねていた・・・ そんな心地よく酔える酒を目指しています。 ※栽培醸造蔵とは農業から醸造まで責任を持って行なう酒蔵のこと、『栽培醸造蔵』は泉橋酒造株式会社の登録商標です。
泉橋酒造は、「酒造りは米作りから」の信念のもと、全国でも珍しい「栽培醸造蔵」として海老名市をはじめ近隣地区で酒米栽培から精米・醸造まで一貫して行っています。 太陽と大地の恵みをいっぱいに受けて育んだ信頼できる米を丁寧に仕込む、それが私達の酒造りです。いづみ橋を囲みながら仲間同士で話が弾み、杯を重ねていた・・・ そんな心地よく酔える酒を目指しています。 ※栽培醸造蔵とは農業から醸造まで責任を持って行なう酒蔵のこと、『栽培醸造蔵』は泉橋酒造株式会社の登録商標です。
赤とんぼに込める酒造りへの思い

日本で昔から好かれている昆虫に「赤とんぼ」があります。特にここ関東地方では「秋アカネ」という種類が多いようですが。
その昔私達の祖先は、日本の国のことを「秋津島、稲穂の国」(秋津・・・赤トンボの意)と呼び表し、「夕焼け小焼けの赤とんぼ・・・」という歌にも「赤とんぼ」が登場してきます。この赤とんぼは、お米が育つ田んぼでお米と一緒に育っていることをご存じでしょうか。

泉橋酒造のお酒は、この赤とんぼが育つ同じ田んぼで育つお米から仕込みます。お酒は、お客様のお口に入るデリケートなもの。泉橋酒造は、お客様が安全で安心できるお酒を醸すために、減農薬栽培や無農薬栽培にも取り組んでいます。私たちが米の栽培時の農薬の使用量を減らすことで、赤トンボの数も増えてくると同時に他の動植物の命も育んでいきます。秋の空にたくさんの赤トンボが飛び交う、そんな故郷をつくるために、そして、お客様に安心して頂けるお酒をお届けするために泉橋酒造では赤トンボをシンボルマークとしています。
全量純米酒の酒蔵です
泉橋酒造は、米と米麹を原料とする純米酒のみ(純米大吟醸、純米吟醸を含む)を製造しており、これは全国的にもまだまだ例の少ないようです。日本酒は古代より米と米麹を原料として造られて来ています。私たちは、その伝統をしっかりと次代へ繋いで行きます。
日本酒の伝統は純米酒

伝統的な麹ふたを使用した麹作り
地域の農家と取り組む酒米作り
泉橋酒造は、「さがみ酒米研究会」という原料米の研究・栽培会を組織しております。この研究会は、地元の酒米生産者、JA、そして、神奈川県の農業技術センター等のお力をお借りしています。酒米の栽培地域は、海老名市、座間市、そして、相模原市に広がり、約44ヘクタール(平成29年度)余りの栽培面積になり、原料米の90%以上を地元産でまかなっています。また、会員農家は全員環境に配慮した農業を率先して行っております。泉橋酒造は、上記44ヘクタールのうち、約7ヘクタールを自社で栽培しています。
田植え機に酒米の苗を積み込み中。1反に20枚の苗箱が必要です。

8月半ば、各々の田を全会員で見て回ります

刈取り時期の見極めも大切な技術
自社精米
泉橋酒造は、米作りから精米、そして、醸造まで一貫して取り組んでおります。私たちは、米作りと同様に精米作業も私達の大切な仕事と考えております。毎年夏場の天候は変わり、一年として同じ天候の年はありませんが、地元栽培された同じ品種のお米でも、農家や田んぼの位置が変わることで少しずつ性格が変わってきます。その生産者ごと、田んぼごとの特徴を見極め、日本酒へと醸していくためには、他所へ委託せずに、自ら精米作業を行うことはとても大切なことだと私たちは考えています。「精米は酒造りの魂」とも云われます。私たちは、お客様のためにごく普通のことを当たり前に行っています。 ※日本酒業界では精米作業は委託精米が一般的です。
収穫された酒米、生産者毎、品種、圃場ごとで管理します

醸造用精米機、新中野工業製NF-26

精米後のお米。精米歩合40%
泉橋の挑戦と責任
地元の農業経済と共に歩む
 泉橋酒造の農業活性化への取り組み、農業にまつわるお話をご紹介します。
泉橋酒造の農業活性化への取り組み、農業にまつわるお話をご紹介します。
地元農業の一部としての泉橋酒造の存在
泉橋酒造は、神奈川県の西部のそびえる大山と丹沢の山々、そこを水源とする相模川の豊かな流れが作り出す海老名耕地の存在。そして、その耕地から育まれる豊かな農産物があったからこそ、私たちの酒蔵は始まりました。私たちは、太古よりの昔より続く地元の農業の一部であると考えています。私たちの酒蔵は、私達だけのものではなく、農業に携わる方から、お酒の販売に携わる方、そして、愛飲家の方々みんなのものと考えています。 田んぼも酒蔵も未来からの預かりものです。
相模原市の田名望地河原の圃場

酒販店さんや飲食店さん達と一緒に田植えを行う田植えイベント。2014年で19年間連続開催中。
地域の農業活性化
平成9年(1997年)以降、 泉橋酒造は「さがみ酒米研究会」の会員農家と連携し、地元での酒造用の酒米の栽培面積を少しずつ増やしてきております。平成27年(2015年)現在、私たちの栽培地は海老名市の全域、座間市の新田宿、相模原市の田名・望地河原、諏訪森下(大島)となっております。それぞれの地域で多数の農家さんの田んぼを耕作させて頂いております。また、耕作させて頂く田んぼには、休耕田や荒れた田などもありますが、逆に私たちが耕作することで地元の田園風景が守られ、農業環境の保全にも役立つことができています。泉橋酒造は、地域の方々と共に明日の農業を考えていきたいと考えております。
田名望地で休耕田を元に戻す2012/04

田名望地で休耕田を元に戻す2012/04

環境保全の取り組み ~とんぼを守る農業~
未来から預かっている田んぼだから、なるべく良い状態で守っていきたい、と私たちは考えています。具体的には、化学農薬の使用量を抑えることもひとつです。お米を栽培する場合に使用できる化学農薬基準は(神奈川県の慣行栽培基準)14成分です。(これは全国でも最も少ない都道府県になります。)そこで、私たちは種モミの消毒の際には化学農薬に頼らない温湯消毒(おんとうしょうどく)を行い、低肥料でお米を育てることで、虫や病気を寄らせない健康的な栽培方法をとっています。平成23年の化学農薬の使用量は、神奈川県の慣行栽培基準の6割減でした。また、泉橋酒造で栽培する品種に関しては、農薬を91%~100%減に成功しています。 また、田んぼをより健康的にし、また、動植物を豊かにしていくために神奈川県や水利組合、海老名市と協力し、冬場田に水を張る「冬期湛水(とうきたんすい)」の実験なども行っております。
初期の除草剤の代わりに米糠を散布。結構な労働量になります。

蔵の北側に広がる冬期湛水の実験田。

大豆農家さんとの打合せ・勉強会
楽しい田んぼの生き物調査
しかしながら、農薬を減らしても、冬場田に水を張っても、実際にどんな効果があるのかは私たち人間にはわかりづらいもの。そこで、田で育つ生き物の調査を泉橋酒造では毎年行っています。具体的には、特に昆虫を捕獲しし記録に留めていくことをしています。田んぼで生きる彼らへのまなざしを向けることは、自然と環境保全していこう、という気概に繋がります。また、その気概は美味しいお酒へと結びつくはずでもあります。 最近では、地元の小学校のサマースクールで「田んぼの生き物教室」を出前して行うようにもなっております。
田んぼの生き物調査2008年~

調査で捕獲されたアジアイトトンボの雌

小学校のサマースクールでの田圃の生き物教室の様子
さまざまな神奈川の恵みをご紹介
地元・神奈川県にも以外にもたくさんの農産物があります。たとえば、小田原市の曽我の梅もとても歴史があり、海老名市の苺も県内ではもっとも生産量があります。泉橋酒造では、これらの梅や苺を譲って頂き、弊社の純米酒に漬け込みリキュールの製造も行っております
神奈川県小田原の生梅

左から、大吟醸梅酒、純米梅酒、純情いちご酒

純米大吟醸に生梅を漬け込んだ梅酒のラベル